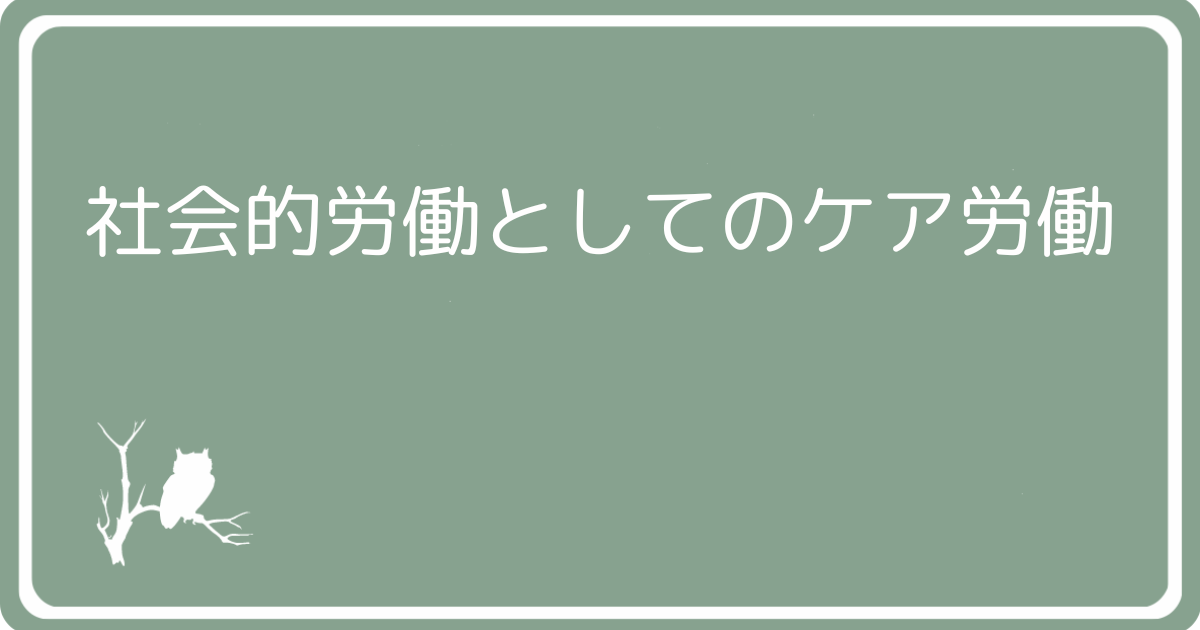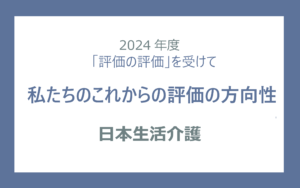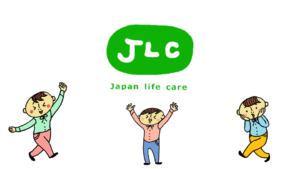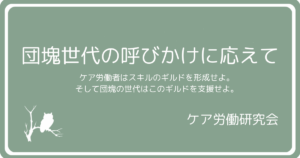ケアの社会化
ケア労働の誕生
ケアの社会化という言葉が一般的に使われるようになったのは、介護保険の導入(2000年)を契機としている。いうまでもなく、その背景には高齢者介護の社会問題化がある。高齢者への介護を家族や地域に委ねておけば、人々の社会的な活動が制限されることが大きな課題となったからである。
そして、今日では、ケアは社会が支えるものとして社会的な合意が得られている。ケアの社会化とは特定の個人にケアの負担が集中するような体制から、社会全体で負担を担うような体制への移行であり、そのために、ケアをこれまでの奉仕や互恵から金銭関係へと転換することによって、契約の自由とともにケアサービスへのアクセスを保障した。
ケアの社会化のもう一つの軸は、ケア労働という新しい職業を作り出したことである。今日では、ケア労働は一つの新しい職業分類となり、さらに数多くの養成機関が誕生するなど、ケア労働の大衆化が一挙に進行している。
ケア労働は、ケアの社会化を担う新しい労働(社会的労働)といわれる。しかし、ケア労働について語られることは少ない。はたしてケア労働とはどのような労働だろうか。他人の世話をするという、古くからあると同時に典型的な現代の労働でもあるケア労働に社会的労働として形を与えることが必要である。
低賃金そして奉仕する労働
ケアは「多くの人が『やりたい』とは思わないダーティー・ワークである。他方で、ケア労働は低技能単純労働であるため潜在的な担い手(代替的労働力)が多く、低賃金の仕事になる……相手に配慮しつつその指示に従属し、ニーズに受動的に応ずる仕事としてのケアは、一言で言えば他人に『奉仕』する仕事である」(堀田義太郎)
「ケア・再分配・格差」 倫理学/生命倫理学 現代思想 2009.2 青土社
ケア労働は労働集約型の単純労働(すなわち低賃金な労働)であり、ダーティー・ワーク、劣等労働だといわれる。頭脳労働に対する肉体労働、技術労働者ではなく技能労働者。求められるのは滅私奉公と自己犠牲であるという。要は、人が「やりたくない」仕事ということだろう。「ケアを女性に押し付けている」という主張も端的にそのことを示している。実際にケアを支えているのは多くの非正規労働者である。
このようなケア労働の現状に対して、通常課題として示されるのは低賃金や格差、総じて基本的に「金の問題」である。確かに、今日ケア労働を取り巻く多くの問題が金によって解決可能であり、実際に多くの論者が低賃金の改善の必要性を主張している。しかし、ケア労働の問題を低賃金として労働一般の問題にしてしまうことは、かえってケア労働固有の課題と可能性を奪うことにもつながるだろう。
ここでは、ケア労働という労働のあり方に焦点を当ててみたい。なぜなら、ケア労働者の直面している問題は、低賃金や人材不足の問題にとどまらず、この著しい市場社会の中で今日の労働が置かれている姿を典型的に示していると思うからである。
ケア労働の特徴
市場の外部の労働
それでは、3K労働でありやりたくない労働などと言われながら、ケア労働はなぜ若い人を惹きつけているのだろうか。それは、ケアが人の役にたつ仕事だからと考えられているからである。
「ケアワーカーたちの多くは、利用者と自分という狭い世界のなかで創意工夫を凝らしながら懸命に働くことに喜びを感じている」(阿部真大)
阿部真大「働きすぎる若者たち」生活人新書 2007.5.10
ここでは利用者との相対の人間関係がケア労働の魅力であると語られている。もとより、惜しみなく与える人間関係とは市場社会の中で失われた家族や仲間共同体のことであり、あるいは、奉仕、互恵、相互扶助、友愛の関係である。しかし、市場社会において労働は生活の手段として位置づけられており、人間関係もまた貨幣を介して成り立つとされる。労働力商品の交換である。「金で買えないものはない」(堀江貴文)のだ。
一方で、ケア労働は、金銭の授受を抜きにして豊かな人間関係が労働として成立する珍しい世界である。それは、市場原理と異なる原理を持つ労働であり、市場原理に統合されない市場の外部の労働である。そしてまた、このことがケア労働に固有の問題をもたらすことにつながっている。
機能の非対称性
ケア労働は、人間の日常生活活動の技能(動作と行為、作法)の問題に介入する労働である。そして、そこには常にケアをする側とされる側という一対一の関係が存在する。両者の間には技能と役割の非対称性がある。この役割の非対称性とは身体的であると同時に社会的な差異であり、そのことがケア労働にサービス労働一般に解消できない特徴を与え、同時にケア労働者という「専門職」を作り出す。
日常生活活動の技能と一口にいっても、大きく運動技能と社会的技能に分けられる。一般的にケアは身体的な機能低下に対する支援のことだと思われがちであり、社会的技能についてはなかなか理解されにくい。社会的な技能は運動技能と連続しているが、しかし、身体的な機能低下のレベルがそのまま日常生活活動の遂行のレベルを決定するわけではない。
たとえ機能低下のレベルが同じであったとしても、性別や年齢、職業や教育歴、環境などの多くの要因で個人差がある。社会参加など、日常生活活動以外の活動ではさらに差が出る。加えて高齢者の場合には世代的な特徴が大きな要因として加わる。このような著しい個人差の存在が社会的技能の低下に対するケアをわかりにくいものにしている。
社会的技能は身体的技能のように道具や機械に置き換えることができない。である以上、いくら科学技術が進歩してもケアサービスがなくなることはない。実際、医療は身体的機能の回復・代替に向けて著しい進歩を遂げている。機能の代替においては人工股関節や臓器移植などはいうに及ばず、遺伝子治療までも射程に収めている。
しかし、医学が科学として進歩を遂げたのは、その技術行使の対象を身体に特定したからである。医療は社会的技能の低下には介入しないし、できない。ここに、日常生活活動の技能(身体的及び社会的)の低下に介入するという、医療とは異なるケアサービス独自の領域、ケア労働の専門性の領域が存在する。
相対の関係
ケアは通常、ケアする側とされる側との一対一の関係で行われ、両者の間には技能の非対称性がある。この技能の非対称性はその人の身体から切り離すことができないから、一対一の関係は容易に「あなたと私の関係」、すなわち実存的な関係を作り出す。そして相手が弱者であることがこの関係を加速する。
「利用者の多くが、家族から見放された『かわいそうな存在』」であり、また「利用者とケアワーカーとの関係が非常に密接」である。そして、「目の前に困っている人がいる。彼らの気持ちを理解し、助けられるのは自分だけだ。見捨てるわけにはいかない」(阿部真大)。
一対一の関係の中で、ケアする側はケアされる側の力になりたいと願う。そこでは、両者の間に密接な関係(同感の関係)が発生する。と同時に、ケアする側に「ケアの心」をも発生させる。
ケアされる側は本来的に弱い立場であり、他者への依存関係によって拘束される。そうでなければ生活できないからである。この依存関係が、両者の間での上下関係や差別をも発生させ、あるいは、逆にケアされる側がケアする側の無抵抗を逆手にとって理不尽な自己主張を押しつけたり、不満のはけ口とすることもあるだろう。弱者であることがそのまま誠意や真心を受け入れる存在であるとは限らない。
同感の関係
このように、ケアはケアする側とケアされる側との間に同感の関係を発生させる。しかし、同感の関係を願って感情交換を行うことは、ケアに限ったことではない。同感の関係を願うことは、人にとっては極めて自然な事であり、人はこうした感情交換を繰り返しながら日常生活を送っている。
こだまでしょうか 「遊ぼう」っていうと 「遊ぼう」っていう。
「馬鹿」っていうと 「馬鹿」っていう。 「もう遊ばない」っていうと 「遊ばない」ってい
う。
そうして、あとで さみしくなって、「ごめんね」っていうと 「ごめんね」っていう。
こだまでしょうか、いいえ、誰でも。(金子みすゞ)
(金子みすゞ「こだまでしょうか」
「こんにちは」とあいさつすれば、相手もまた「こんにちは」と返事を返す。相手がうれしそうな顔をしていれば、「よかったね」と同感の言葉をかける。そして相手も自分の感情が理解されたとしてうれしいと感じる。ここに同感の関係の実現、すなわち感情交換が成立する。感情交換が成立すれば、働きかけた方もうれしいと思うし、成立しなければ働きかけた方は残念に思う。
「私たちは、利害関係がなくても他人に関心を持ち、他人の感情や行為に同感しようとする。私
たちは、他人も私たちに関心を持つことを知り、自分の感情や行為に他人が同感してくれること
を望む」(アダム・スミス)
堂目卓生 「アダム・スミス」 中公新書 2008.3.25
人は相手に同感してもらおうと、時にへりくだったり、あるいは自分を大きく見せたりと自己の振る舞いを調整する。家族など親しい関係であれば自分の感情の赴くままの言動も許されるが、他者に対してはそうはいかない。顔色を見(伺い)ながら、瞬時に自己の感情表出の調整を行う。
そしてさらに、相手の反応(感情表出)を確認する。人はこうした経験を繰り返しながら社会的な規範を内面化していく。そして、自分が働きかけた相手の反応を確認することで自分の感情もまた確認される。こうして、感情交換が繰り返されることで自己が形成される。
感情交換の成功体験がなければ対人関係に臆病になってしまい、閉じこもりの遠因ともなる。子どもは、親との感情交換を通じて同感関係の実現と挫折を繰り返しながら世の中の規範(善悪や価値)を身に着けていく。一方、SNS では相手の表情や振る舞い方ばかりか性別や年齢すらわからない。あるいは、コロナ禍においても子どもの間での会話の機会の減少がそのまま対人関係のスキルの不十分性につながることが指摘されてもいる。
それでは、実存的関係の成立を強く願う場合はどうだろうか。例えば中学生時代のラブレターを想起しよう。手紙を出しても返事が来るかどうか不安でたまらない。あるいは挫折を恐れ、自分をよく見せようと演技をすることも普通にある。その裏には、本当の自分の気持ちを分かってほしいという欲求があり、あるいは、偽りの心に後ろめたさを感じ、正直でなければいけないとも思う。かし、あれほど同感関係の成立を願って一言一句に心血を注いだとしても挫折は常にある。
感情交換の成否の鍵を握るのは自分ではなく相手だからであり、そこに半信半疑の地獄が生まれる。だからこそ片想いは歌にもなる。このように、他者との感情交換が成立するかどうかは危険を伴うカケなのであり、日常生活においてそんなカケを続けるわけにはいかない。時候のあいさつや当たり障りのない会話、マナーなどはスムースな同感関係の成立を助けるための人びと知恵である。
役割演技
ケアの社会化に伴い、ケア労働は弱い者のお世話や代行から自立支援へと大きく舵を切った。指示や命令によるものでも、また義務でもなく、ケアする側とされる側での共同の事業として自立のためのプログラムが遂行される。そしてそのためには、両者がそれぞれに期待する役割を演じることが求められる。
役割の遂行とは、それぞれが置かれた状況に応じて、周囲が要求し期待するように行動することである。これを役割演技という。ケアにおける協力関係とは、双方が役割を演じながら、同感の関係を作り出していくことである。しかし、ケアの場合は、ケアをする側とされる側に技能の非対称性があるから、役割演技の遂行はとりあえずはケアする側の役割となる。ケアをする側は同感関係の実現に努めるが、しかし、だからといってケアをされる側が常に同感関係を維持しようと努めるかどうかはわからない。いくら働きかけても、快・不快などのその時々の気分や感情が優先して同感関係を壊す場合もあるだろう。あるいは、感情の赴くままにケアする側に同感を求めるかも知れない。そこではお互いの感情がすれ違い、感情の不等価交換が発生することが普通である。ケア労働はこうした危うい同感関係を維持しようとする労働である。
同時に、ケアはお世話することでも相手のいいなりになることではないから、ケアされる側は自ら役割演技ができるように促され誘導される必要がある。ケアされる側に役割演技を促すことはケア労働者にとっての技能(スキル)である。そこでは、ケア労働者の一つひとつの言葉や仕草、表情、総じてケアをされる側とする側の両者の関係性の作り方までが技能である。そして、ケア労働者とは演技する者(役者)である。役割の遂行のためには、相互の社会的な規範(社会的常識・ルール・約束事・しきたり)の共有が前提となる。規範のレベルは画一的なものではなく様々であるが、度が過ぎる、やり過ぎなど、社会的な許容のレベルは存在している。
自己決定もまたその社会の規範と節度の中にある。いくらケアされる側の感情が優先されるとはいっても、暴力行為やセクハラについても受け入れろとはいい難い。あるいは、子どもではないから、快・不快の感情のままに、感情を爆発させれば非難の対象ともなる。感情を爆発させないこともまた、ケアの技能である。しかし、ケアされる側の役割というと、たちまち反論がくるかもしれない。お客様は神様だとはいわないが、市場の金銭関係や契約関係がそのままに持ちこまれ、ケアされる側の権利とケアする側の義務が主張されるかもしれない。
あるいは、ケアされる側を「あるがまま」に受け止めるという主張もまた根強い。さらに、心からの同感や共感、心が通い合うこと(ケアの心)が重要であり、演技することは自分を偽ることだと思うかもしれない。よく、「利用者から発せられる『ありがとう』という感謝の言葉が、ワーカーたちの『気づき』の労働に対する最大の報酬であるようだった」(阿部真大)といわれる。「ありがとう」という言葉は同感関係の成立を示すとされるが、しかし、考えて見れば、ケアされる側の「ありがとう」という言葉が本心か役割演技かの区別はできない。
逆に、する側とされる側がそれぞれの役割演技を実践しているのだともいえる。日常生活では、たとえ客であっても「ありがとう」や「お世話になりました」と声をかけるのは一般的なことであり、そのことによって消費者の権利が侵害されるわけでもない。
高齢者のケア
ケアする側への過度の依存を断ち、自立と尊厳を守ることは基本的にケアされる側の責任である。しかし、高齢者の場合、機能低下は年をとるという生物学的自然の結果であり、本人の責任ではなく免責と依存が許されるものと受け取られがちである。
あるいは、素直に運命を引き受けたりはしない。家族や社会に迷惑をかけたくないと思い、また他人に依存したくないとも思う。一方で、弱さに抗い、弱さを認めない、認めたくない。自分は「他の老人とは違う」とも思う。頑固、偏屈などと老人にかかわる形容詞は多く、時に「老害」ともいわれる。すでに述べたように、社会的技能には個人差があり世代的特徴がある。背景にこれまでの人生の歴史があり、世代が共有する独特な振る舞い方としきたり、そこで培われた独自の規範がある。体に染みついた規範もまた生き方の反映である。
であればこそ、高齢者の世代の規範のあり方と見識が問われなければならない。「あるがままの私」ではいけない。嘘だと思うなら、巷にあふれる(男性)老人の生き方の指南本を手に取ってみるとよい。そこには地域の(元気な中高年女性の)コミュニティにいかにすれば受け入れられるかというノウハウがこと細かに記載されている。
人は社会の中で生きる存在であり、社会は「第二の自然」ともいわれる。そこでの自己は社会的自己である。しかし、加齢による機能の低下とともに、忘れられていた「自然」(生物的自然、第一の自然)が顔を出す。この「自然」は、個人は自由で独立した存在である(あるいは、存在でなければならない)とする近代的人間観と齟齬をもたらす。そしてその先に自身の「死」がある。こうした一筋縄ではいかない多様さを前にしてどのようにケアを行なえばよいだろう。
しかし、穏やかに暮らすことを願うこともまたケアである。ケアされる側を日常生活活動の遂行へと促すために、ケアする側は困惑し、うろたえながらも絶えずアプローチを繰り返す。そして、隙をみながら相手の技能(スキル)に介入する。それは、一方的な介入としてではなく、同感関係を保ちながら、ケアされる側が感情交換の基本的なルールに従って自らの感情をコントロールできるように誘導する試みである。「スキルに介入するスキル」とはそのことだ。