科学的であることと経験技術
学校では、福祉の支援は科学的でなければならないと教える。しかし、実際の援助のスキルは現場で学べとされる。はたして福祉の支援は科学的でなければならないか?
福祉教育の特徴
大学や専門学校など福祉にかかわる教育・研究の場は数多い。もちろんそこでの専門教育のレベルは国家によって定められているが、一方で、学校で学んだことが役に立たないとも言われ、職員の育成は現場に丸投げされる。一体に支援の教育とはどのようなものか。
社会福祉の専門性は、「スペシャリストのような奥行きの深い専門性ではなく、ジェネラリストのような奥行きは浅いが幅の広い専門性」(これからの社会福祉 有斐閣1999年)とされる。例えば、支援に携わる職員に必要なものとして、吉澤英子氏は「(児童養護の専門性には)社会福祉学のほかに心理学、社会学、精神医学、小児医学、その他の医学、教育学、法学、住居学、家政学などについての基本的知識・技術」が必要だという(「季刊 児童養護」26号)。
あれもこれもと詰め込むことが日本の福祉教育の特徴であるが、必要とされる知識の範囲のあまりの広範さに驚かされる。
さらに、福祉に関する教育のもう一つの特徴は、「科学的」であることにある。
社会福祉援助は「科学的かつ専門的に展開されなければならない」。あるいは、社会福祉援助の過程は「科学的かつ専門的な方法による一連の援助行為が局面を追って展開され……」(前掲「これからの社会福祉」)
あるいはこういうものもある。
介護の提供には「身近な看護職から謙虚に医学的知識や援助技術の基礎を学ぼうとする姿勢が必要だ。……介護職は看護職に必要とされる情報を的確に伝えることで利用者のために役立つことが出来る。すなわち自分たちの存在が活かされるのである」(鎌田ケイ子 「シルバー新報」2009.7.7)
ここでは、「医学的知識と援助技術の基礎」(科学的であること)が支援の専門性であり、それ故に介護(技能)に対する看護(看護)の優位性があると主張されている。要するに脳が考え手足が動く。
科学的でありたい
看護における専門性を科学によって根拠づけるという主張は、かねてより看護論の特徴であった。
川崎みどり氏(日本赤十字看護大学名誉教授)によれば、看護には「看護は技術か技能か」、「看護師は専門家か、それとも職人なのか」という問いをめぐる長い歴史があるという。
ここでいう科学とは科学技術(近代テクノロジー)のことであり、演繹的で法則的な説明ができるものとされる。そして、「技術とは人間実践(生産的実践)における客観的法則性の意識的適用である」(武谷三男 1911~2000年)。
技能(スキル)が言葉に置き換えられて知識へと変換され、誰がやっても同じ結果が得られるようになる。技能が積み重ねられて技術となり、科学の仲間入りをする。川崎みどり氏の看護論はこうした組み立てとなっている。川崎氏は、武谷技術論の看護への「意識的適用」だとされる「実践的看護マニュアル」を作成し、これが「よりよい看護」という言葉のルーツともなった。
確かに医学はそれまで医術や占星術、呪術、魔術などと混然一体のものから、感染症の原因となる細菌の発見によって原因と結果という因果関係を手中にして科学となった。人体における「客観的法則性」の発見である。そして看護もまた医学のように科学でありたいと願っている。
それでは福祉はどうだろうか。福祉もまた科学でありたいと願っている。そのためには、日常の支援の専門性が科学的に実証されなければならない。
「すぐれた実践が一般化、普遍化できず、職人芸の域で終始し……経験から生み出されるのがカンでとどまって」いる限りは、「経験に意味を見いだ」すことはできず、「施設処遇の専門職(性)のレベルアップは図れない」。よって、技能(スキル)の属人性(職人芸)から脱して実践の中に「意味や法則性や因果関係を発見、追求」する「福祉専門方法としての研究、理論化」が必要である。と、ここまでは川崎氏の看護論と同じ組み立てである(前掲「これからの社会福祉」)。
しかし、問題はここから始まる。にもかかわらず、福祉において実践研究はこれまで十分に行われてこなかった。それは、「社会福祉施設が日常的に提供している食事、掃除、介護などの日常的・基礎的生活領域の処遇は、あまりにも当然のことであるために」実証研究や理論化は低調なのだと言う。ここで「科学でありたい」という願望はいち早く挫折している。
人々の日常生活活動にかかわる「あまりにも当然のこと」とは実は「暗黙知」といわれるような技能であり経験技術である。それが技能であることは経験し学ばなければ身につかないことであることからもわかる。そして言葉にして対象化できないからこそ、「暗黙知」と言われ、身体と切り離せないからこそ身体知とも言われる。
自然を扱う技術
もとより、属人的なスキルを法則性や因果関係に転換して技術としすることが進歩であるという思考は根強く、くり返し登場する。確かに、物を扱う場面では技能の技術化が絶えずイノベーションを起こしながら(それでも一定のカンやコツは残るが)産業の発展を促してきたことは事実である。しかし、人間という自然を相手にする場面では事情が異なる。
17世紀以降科学が確立されるまでの人類の長い歴史の中で、そもそも技術とは経験技術のことであった。そこでは、暦の発明やピラミッドなどの巨大土木技術、あるいは様々な医術や呪術、魔術が一体のものとして存在していた。それらは神の恩寵であったかもしれないし、時に門外不出の秘儀として代々受け継がれてきたものかもしれない。そしてこのような技術は自然や生物を扱う技術、端的に経験技術であり、原理は明確ではなくても問題の解決にあたってきた。このような自然を扱う技術はまた改良や工夫を積み重ねた長い歴史(経験)を持っている。
たとえば、農業には自然の変化を読み取りながら農法や品種改良を積み重ねてきた。例えば、中尾佐助氏は著書「栽培植物と農耕の起源」の中で、ムギやイネ、バナナなどの栽培植物の多くが何千年もかけて改良発展されてきたと述べている。
今日においても、有機農法をはじめ、発酵技術、汚泥処理など生物を扱う技術は多い。そこでは、温度、湿度、天候を感じながら、なめて、あるいは食べて味をみる、においをかぐ、触ってみるなど、五感を使って変化を読み取りながらの対応が行われている。
ひるがえってみれば、科学のいう自然の客観的法則性が物理化学的な法則性に基づくものである以上、それは1対1の因果関係であり、科学は因果関係にないものの説明は原理的にできない。
それはモノの論理であり人間や生物の論理ではない。したがって、支援のスキルや専門性が「科学的」なものでなければならないという根拠もない。生活の中での技能は科学技術とは性格の異なる「もう一つの技術」であり、むしろ経験技術でなければならない。
生物にとっての問題解決とは環境に対する適応であり、進化として結果する。進化には科学的な必然性はなく、因果関係は事後的に説明される。だから、「進化論は形而上学」だといわれたりもする。
科学への固執
さて、福祉学の専門家たちはなぜ、ここまで「科学的」であることにこだわるのだろうか。普段私たちは福祉を科学とは意識しないし、科学的福祉という言葉は聞かないように、福祉学者を科学者とは呼ばない。「問題解決の手法を見出す実践研究が低調」なのは、職員がカンの赴くままに職人芸を繰り返しているのではなく、現場での実践のなかで「仮説と検証」を日常的に繰り返しているからであり、改めて(科学的な)実践研究の意義を感じないからだ。
福祉学者が科学的でありたいというこだわりの謎は、単に学の確立の方法論上の問題として考えても解けない。今では不思議な感じもするが、科学的であるということは一つの時代のイデオロギーであった。戦後、学者や知識人にとって科学的であることはそのまま進歩的であり民主的であることだった。すなわち、「人間実践における客観的法則性の意識的適用」という技術論はマルクス主義労働論と結びついた社会主義的変革のイデオロギーであった。もちろん例えば科学的社会主義という言葉があるように、科学的と呼べば科学になるわけではない。ここでの科学的とは、自然科学や科学技術のことではなく、たとえて言えば、柿右衛門「風」有田焼のようなものだから、正確には科学風ということになるだろう。
当時は、科学の進歩は人類に幸福をもたらすと信じられている時代である。かつて科学的であることは、正しく、善で、進歩的であり、非科学的であるといわれることは学者にとって致命的なこととして受け止められていただろう。さらに、先の川崎氏の努力の背景にも、看護が科学であることが医療業界における看護師の身分の向上につながるという事情もあっただろう。
時代は、技術革新によって経済が成長し、まだ公害も原発事故も地球温暖化も知らなかった時代であり、また、ヨーロッパ近代以降の啓蒙主義や合理主義が疑われてもいなかった時代である。そこでは巨大科学に対する不信もなく、原爆もコントロールする側の倫理的な問題(例えば科学者の良心)として考えられていただろう。しかし、今日では科学の進歩がそのまま人類の幸福につながるとは考えられていない。原子力をめぐる問題や環境や生態系の破壊をはじめとして科学がもたらした矛盾が露わであり、また安楽死や生殖、あるいはクローンなど生命をめぐる倫理問題もまた大きな課題となっている。そして、科学はそれ自体では自らを制限する論理を持たないから、今日では社会が科学(という客観的法則性)にブレーキをかけること、社会の名で科学を制限することが当たり前になっている。
ここで印象的なことは、支援の専門性を「永遠の課題」だといってすませてしまう学のあり方である。現場の課題が原理の解明ではなく問題の解決であることが忘れ去られているだけでなく、ここにはかつて看護が技術(すなわち科学)でありたいと願ったような強迫も、そして挫折もない。
ここにあるのは科学には知りえないことはないという科学への楽観的な信頼である。それは、科学は絶えず進歩するから、今はわからないとしても将来は必ず解明されるはずだという確信でもある。そしてまた、医学がそうであったように、わからないことは対象としないという科学の性格も作用しているだろう。つまりは「想定外」ということだ。知りえないことを見ないことによって学が成立し、あとは倫理で補完する。つまるところ、科学(的)でありたいという執着が「もう一つの技術」としての技能の確立の道を閉ざしているのである。
科学からはみ出るケア
さて、果たして看護は科学になったのだろうか。
川崎氏の看護論では、技能を言語化すること知識や技術に転換され、普遍化される、すなわち、職人技という属人的な性格を脱していくことが「よりよい看護」につながると考えられているのだが、しかし、このことが看護をめぐる「技能か技術か」という問題の解決につながったとは思えない。
科学となった医学は身体機能を対象とし、人の日常生活活動を対象とすることをやめた。技術は画一的であり、人間や生活という個別性と多様性を相手にできないからである。このことによって、医学は自らの対象としない、あるいはできないケアという領域を医学の外部に残すこととなったが、看護は日常生活活動の援助にかかわるという課題を捨てることはできず、ジレンマとして抱え込むことになった。また同時に、PTもまたICFの新たな障害モデル(因果モデルからの転換)への対応を課題として求められている。
ひるがえって福祉はどうか。前述「これからの社会福祉」の著者はこうも述べている。
「施設処遇の専門職(性)論議は、古くて新しい問題であり、決着がつかない永遠の課題ではないかという感がする」。専門性とは技能の属人性を脱することとしながら、しかし、「永遠の課題である」というのである。
それは「科学的知識、技術をもっての実践は、職員の人格・価値観などによって大きく左右される。……優れた知識や技術を持った者が、必ずしも良い処遇効果を上げるという保証がない」とも述べているがこの指摘は重要である。ここに、処遇(支援)が経験技術であり、技能の属人性という特徴がよく出ている。人柄もまた技能(スキル)である。
そもそも、後は現場で学べとして教育が現場に丸投げされていること自体、支援の技能が経験技術であることを示しているのではないか。そして現場で学べとか言われているものは学校では教えない日常生活活動の技能(スキル)である。
スキルの自覚と共有
考えてみれば、学が支援の専門性を「永遠の課題」として棚上げしてしまうことは決して悪いことではない。なぜなら、学に期待することなく自分たち考え、決めていくことができるからだ。
支援は技能によって行われ、支援する者はその技能を身体で知っている。「あまりに当然のこと」が言葉にできないのは、日常生活活動の技能が遅れたものだからではなく、言葉で言い表す必要がないからである。「あまりに当然のこと」が無意識に行えるまでに洗練された結果、脳は日常生活活動のコントロールにエネルギーを費やすことから解放されたのである。
支援者にとって必要なことは、技能の技術化や新しい技能の獲得ではなく、すでに持っていて実践している技能(スキル)の自覚と共有である。日々の支援の中で気がつくことを技能の専門性として再確認し、新しい言葉を作り出す。新しい言葉の発明である。新しい言葉は「科学的」である必要はなく、さらに既存の言葉である必要もない。
ここに便利なマニュアルはないから、技能を共有するための方法が問題となる。かつては背中を見て学べというように言われてきたともされるが、そこまで「秘技」化する必要はない。現在行われているOJTやロールプレイイング、SVなど、様々な方法の試行錯誤が必要である。
自分たちだけで考えていてもなかなかわからないことも他者と比較することでよくわかることがある。例えば外国に旅行して初めて普段意識しない日本や日本人のことを理解するようにである。
技能は本来的に個人的な能力でありそれぞれに技能の差はあるから、とりあえず、自転車の練習のように、うまくできる人のマネをしながらやってみることが必要である。そして、経験技術である以上、技能の習得には手間ひまを惜しんではならない。
日常の支援の中で事業所のあちこちで不断に行われる利用者との感情交換の積み重ねのうちに、一つの規範が形成され、共有可能な技能のレベルが析出されるはずである。その技能は個人の身柄を離れて抽象化され、やがて事業所(私たち)の支援のスタイルとなる。その実践のレポートが役に立つだろう。
質問してみる
「ケアの専門性とは何ですか?」
「医療と介護の違いとは何ですか?」
「技術と技能(スキル)の違いはどのようことですか?」
「スキルアップというときのスキルとはどのようなことですか?」
経営層や上司、学者や経営コンサルタントに、さらに研修講師、あるいは第三者評価の評価者に聞いてみよう。それが自分たちの考えを確認し、深めていくための出発点である。
質問に対する答えは、おそらく知識と研修、理念と倫理の強調であろう。そして多くの場合、私の想いや私の経験、私の人生のエピソードなど、総じてやさしさや心構えなどといった精神論(倫理)へとテーマをすり替えていくだろう。あるいは慣れた人なら「あなたはどう思うのですか?」と切り返して煙に巻くかもしれない。要は、ケアの専門家と言われる人たちがケアの技能を認識しているかどうかという問題である。
質問を通じて得られるものは、実は、自分たちの経験以外には何もないという事実である。繰り返すが、このことは私たちにとっていいことなのである。

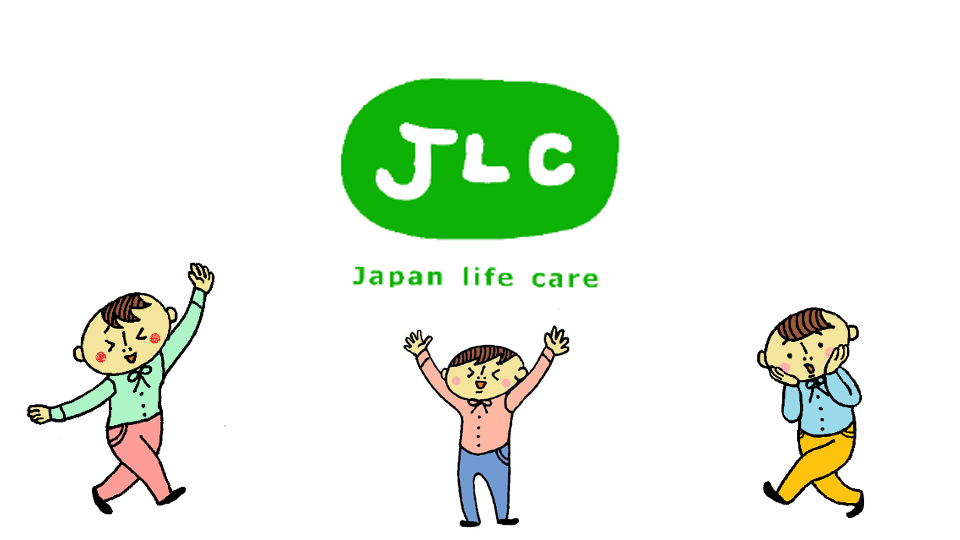
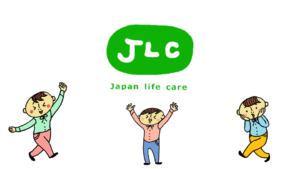

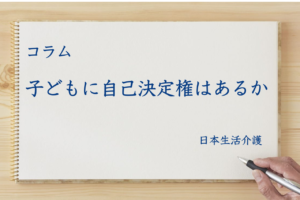

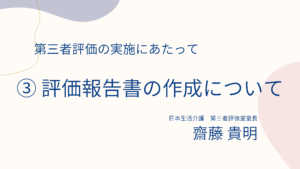
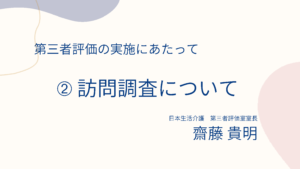

コメント