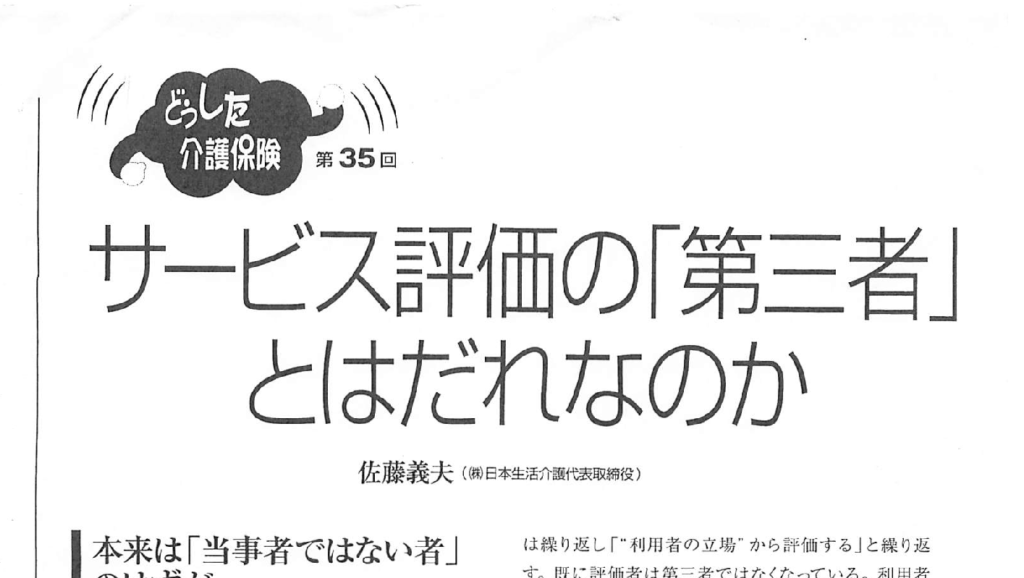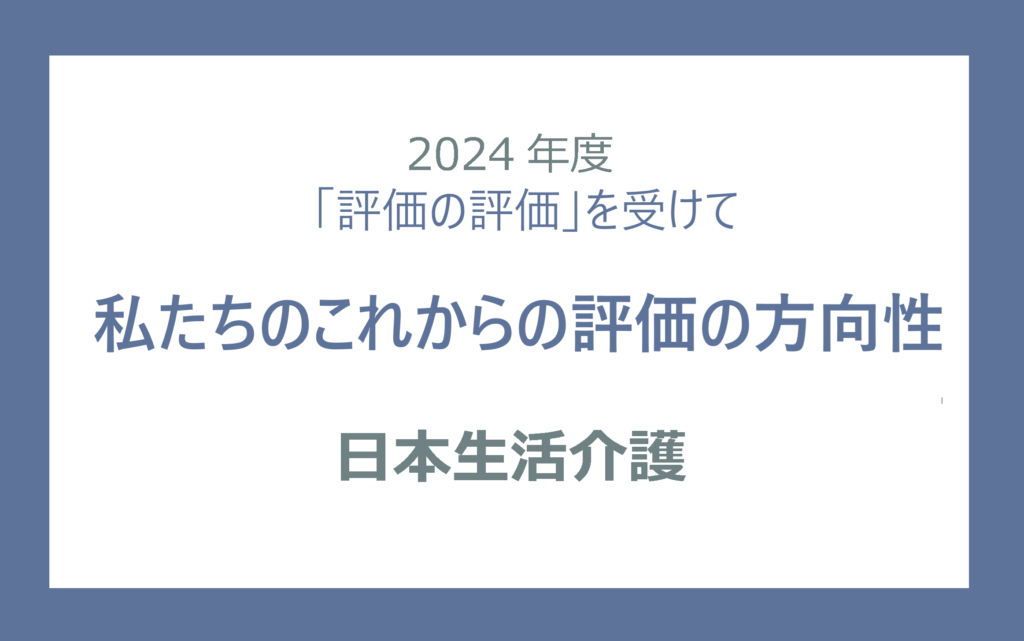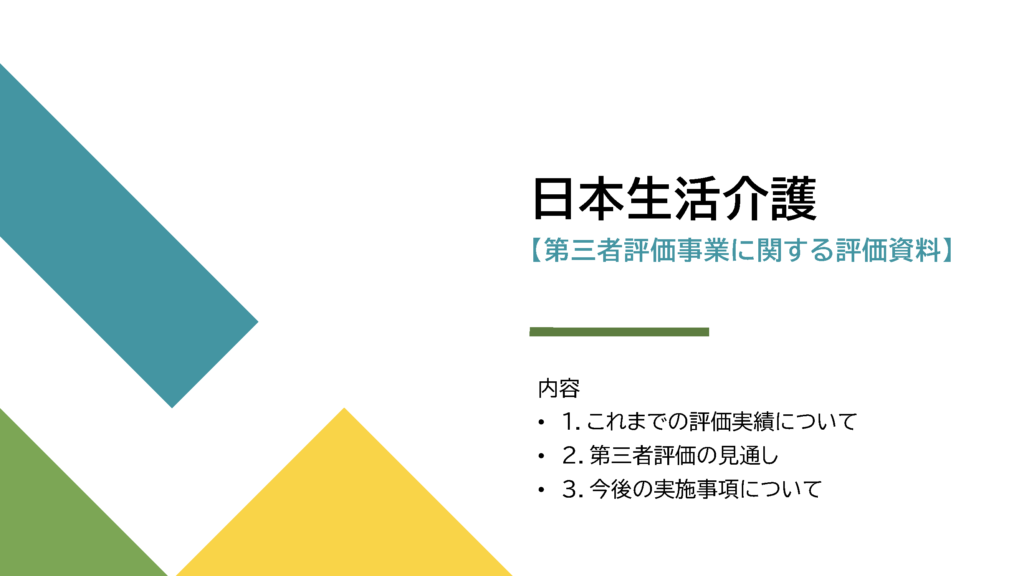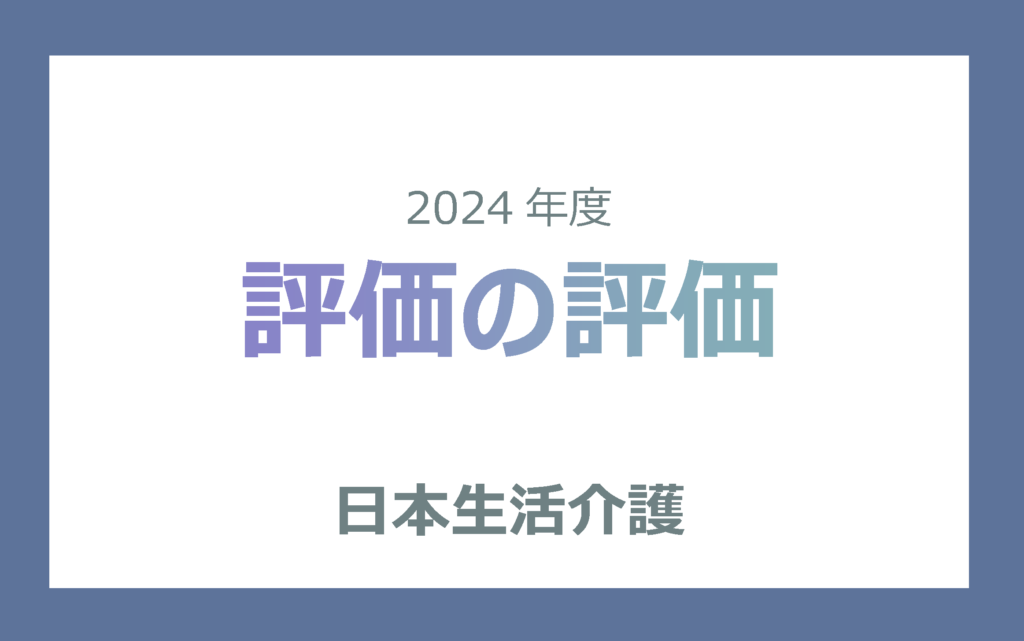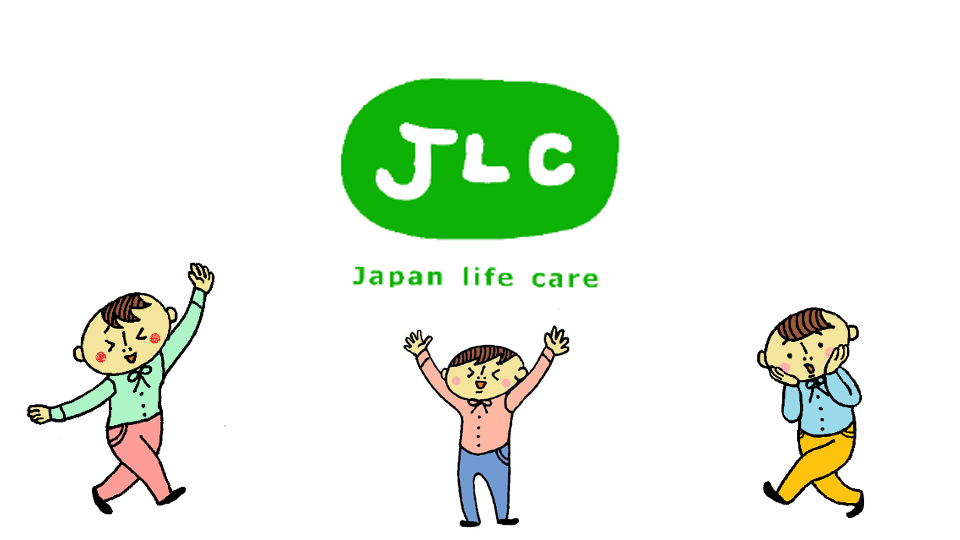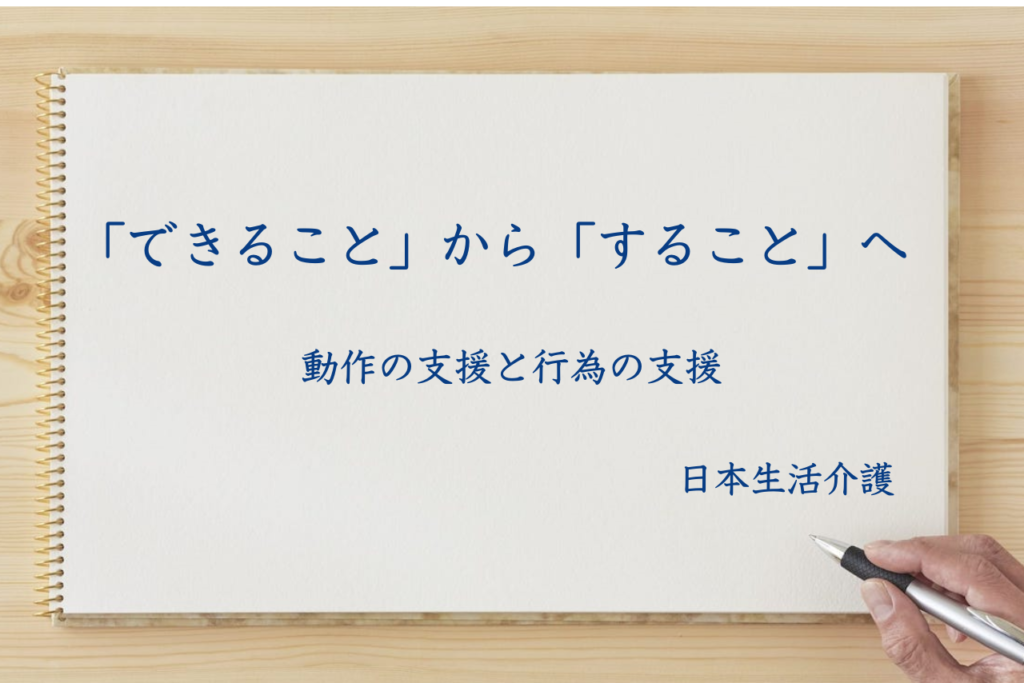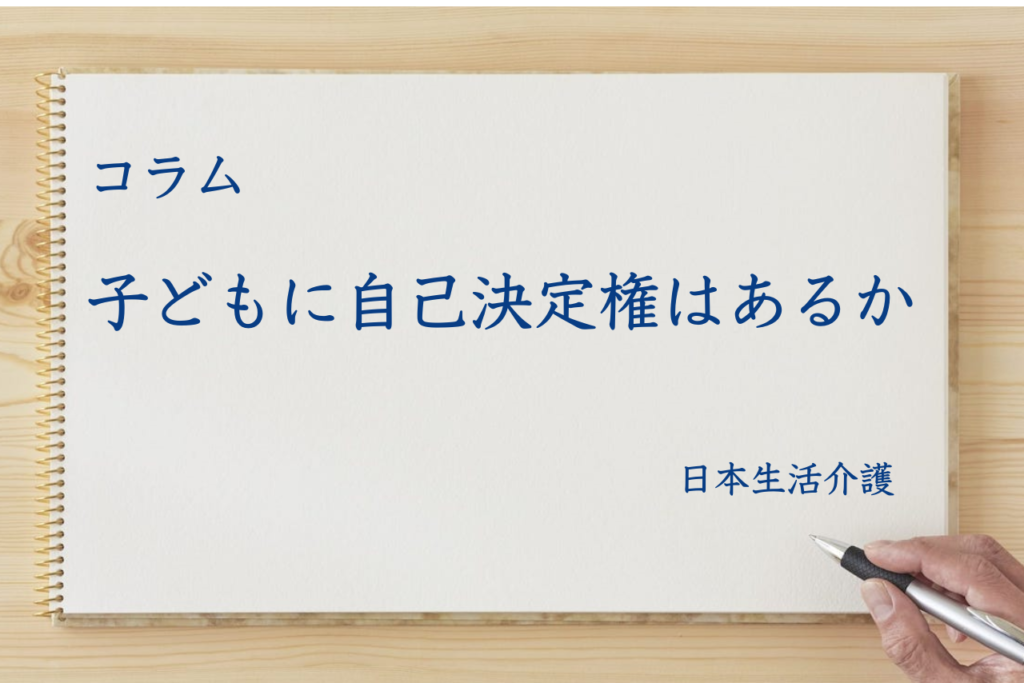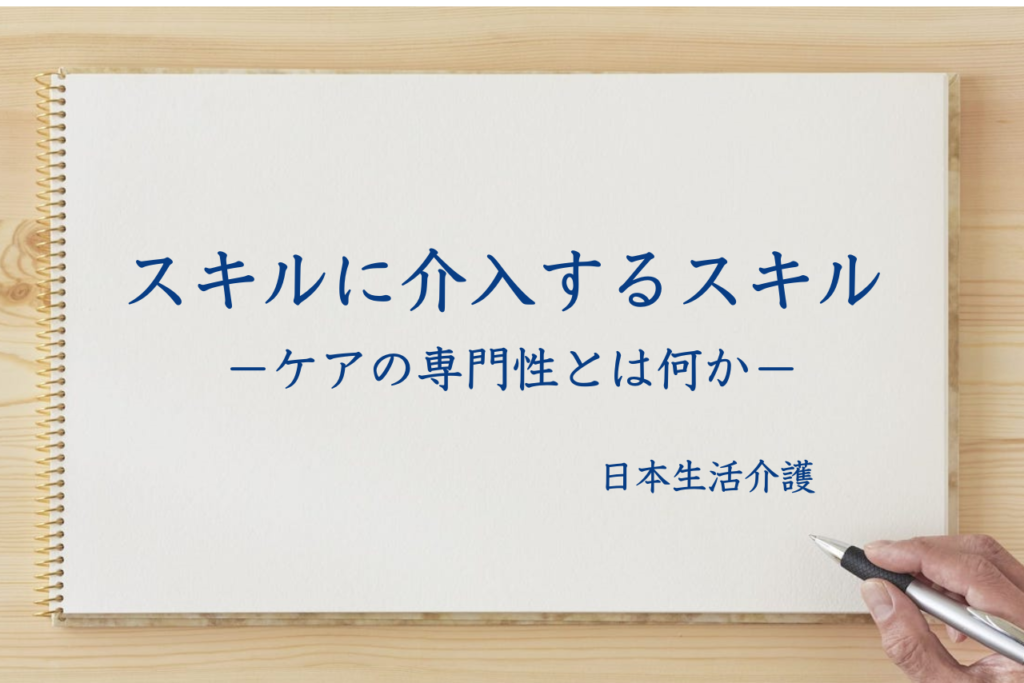評価者の皆様へ– category –
-

サービス評価の「第三者」とは誰なのか
本来は「当事者ではない者」のはずが…… 第三者評価において第三者とは、事業者でも利用 者でもない者、つまり「当事者ではない者」として定義 される。そこに期待されているのは、公正・中立、客観性等、感情と利害の排除である。従来、学識経験 者など... -

今後の評価実施の方向について
-第三者評価事業に関する評価の結果を受けて-024.9.26日本生活介護 PDFファイルのダウンロードはこちらから 2024年6月14日、佐々木貴雄氏(日本社会事業大学 社会福祉学部准教授)、山本雅章氏(静岡福祉大学 社会福祉学部心理学科特任教授... -

第三者評価の概要
この資料は、日本生活介護で「評価の評価」を実施する際の説明資料です。これまで評価機構のガイドブック等で公表されている資料ですが、特に第三者評価の受審を考えている事業所にとっても第三者評価の概要を知る上で参考になると思います。第三者評価受... -

評価の評価
第三者評価の評価を行いました 日本生活介護 第三者評価事業に関する評価結果報告書 024.9.26日本生活介護 2024年6月14日、佐々木貴雄氏(日本社会事業大学 社会福祉学部准教授)、山本雅章氏(静岡福祉大学 社会福祉学部心理学科特任教授)の両... -

科学的であることと経験技術
科学的であることと経験技術 学校では、福祉の支援は科学的でなければならないと教える。しかし、実際の援助のスキルは現場で学べとされる。はたして福祉の支援は科学的でなければならないか? 福祉教育の特徴 大学や専門学校など福祉にかかわる教育・研究... -

ケアの専門性とは何か
ケアの専門性とは何か 相手の心の中にうまく介入していくことが(支援の)スキルである。(都内母子生活支援施設2021年) 資格と機能の非対称性 ケア労働は専門的な労働であり、ケア労働者は専門職であると言われて久しいが、その専門性とは何かについて... -

倫理、道徳そして規範
2021.11日本生活介護 倫理と道徳の違い ケアにおいて倫理は特別な位置を持っている。ケアに携わる者は何よりも倫理的でなければならないというようにである。そして道徳もまた倫理と同じような意味で使われることが多い。両者はしばしば混同して使われる... -

「できること」から「すること」へ
「できること」から「すること」へ-動作の支援と行為の支援 私たちの仕事は、単に老人の動作を介助しているのではなく、もっと広く生活行為を介助しているのだということをぜひ忘れないようにしたいと思います。(三好春樹「介護技術学」1998 雲母書房)... -

子どもに自己決定権はあるか
子どもに自己決定権はあるか 2022.10日本生活介護 功利主義の提唱者であるJ・S・ミル(「自由論」1859年)は自由主義の条件を次のように示している。 「判断能力のある大人なら、自分の生命、身体、財産などあらゆる〈自分のもの〉にかんして、他人に危... -

ケアの専門性とは何か
ーケアの専門性とは何か-2021.10 スキルに介入するスキル 日常生活のスキル 支援のスキルとは、利用者(子ども、障害者、高齢者など)のスキルに介入するスキルのことである。 ここで言う利用者のスキル(技能)とは、日常生活活動を遂行する技能であ...
12