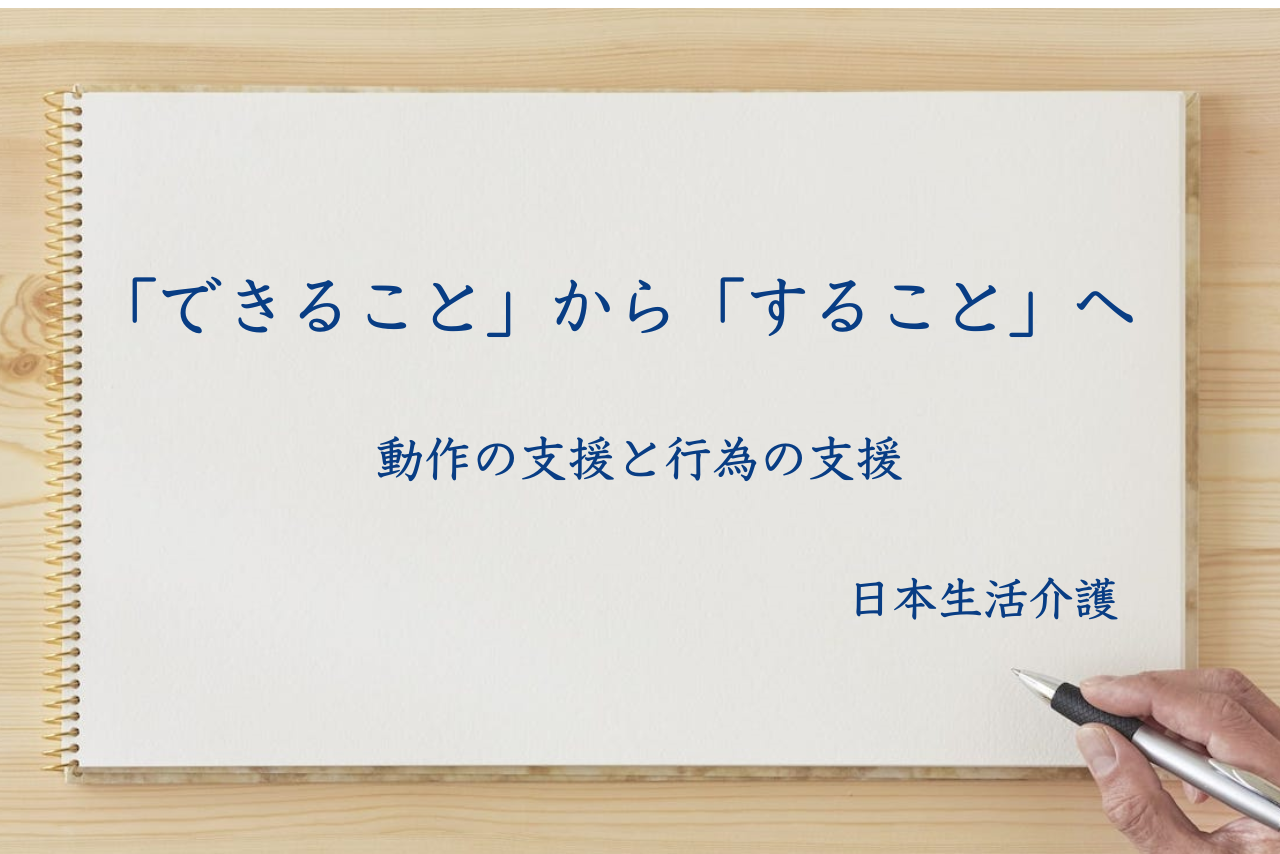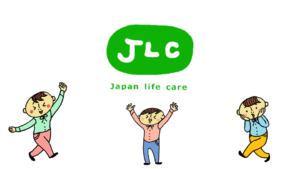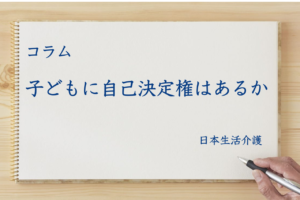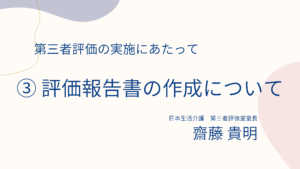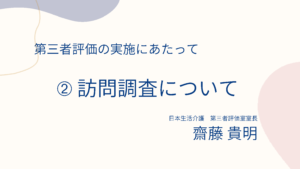「できること」から「すること」へ-動作の支援と行為の支援
私たちの仕事は、単に老人の動作を介助しているのではなく、もっと広く生活行為を介助しているのだということをぜひ忘れないようにしたいと思います。
(三好春樹「介護技術学」1998 雲母書房)
動作と行為
生活リハビリは、介護では「できる(動作)からする(行為)への転換」が重要であると主張する。
日常生活のスキルとは、普通の人が日常生活であたりまえに行っていること、歩く、話す、服を着る、顔を洗う、歯を磨くなどの動作や行為をこなす身体的な能力である。人は発達段階でこのスキルを身に付ける。このスキルは、簡単には言葉にすることができず、人から人へと直接伝えることによってしか他人に渡すことのできない能力のことであり、だから、普段はそれが能力であることは意識されない。
日常生活活動(ADL)は動作(motion)と行為(action)で組み立てられている。多くの場合、行為は異なる動作の組み合わせであり、一つの行為は動作の連鎖として構成されるが、行為は目的や意図(主体的活動)を伴うことで動作と区別される。たとえば、食事という行為は手を動かして食べ物を口に運び、咀嚼して飲み込むといった動作の連続である以上に、会話をしながら食べる、マナーがあるなど社会的なものである。同様に、会話も発語動作の連続ではない。
医療は動作しか見ない
このような動作と行為の違いを理解するためには、医療を考えるのがわかりやすい。医療もケアも、ともに人間の身体を扱う技術・技能であるが、医学の特徴は原因と結果の因果モデル(すなわち科学)にある。そこでは病気には原因があり、その原因を取り除く、あるいは、緩和ないし中和することが治癒につながると考える。医療が目指すのは動作の回復である。つまり、医療は動作しか見ないし、見られない。医療の対象はあくまで生物としての人間の心臓や手足の動きなど(臓器)のレベルでの機能低下である。したがって、生活の質(QOL)など、因果モデルをはみ出す問題に医療は介入しないし、できない。
ちなみに、医療は原因の除去と機能の代替(たとえば人工股関節から心臓移植、はてはDNAの移植まで)を目標とする。IT化、福祉機器、バリアフリーなどもまたこの延長にある。
このような医療の考え方の背景には、脳が指示を出し身体は脳の指示によって動くというデカルト的心身二元論あるいは身体機械論がある。こうした考え方は意外と根強く、例えば介護保険発足当初にも一つの傾向として見られた。
当時、訪問介護の報酬がデイサービスに比べてはるかに高額だった。その背景には、たとえ身体機能が低下したとしてもホームヘルパーを手足の代替として使う(拡張された身体)ことによって自立した生活を送ることができるという考え方が主流であり、一方のデイサービスは幼稚園のようで利用したくないと言われ、普及するどころか全滅とも言われた。当時は認知症の理解があまり進んでおらず、当時のインテリ知識人にとって脳の機能低下は想定外であり、ましてや自分がなるとは思ってもみなかったであろう(私自身はそういった考え方が気に入らなくて、「あなたがはじめるデイサービス」(雲母書房 2012.5)を書いた)。
しかし、実際の所、身体はデカルト的なものだろうか。たとえば、定型動作というのがある。歩く動作、歩幅、速度、リズムなど、誰であっても(人類であれば)おおむね同じパターンを持つ。それは歩くときに消費するエネルギーの最適化を図った結果であり、骨格や筋肉の制約がそうした動きを作り出しているといわれるが、順序はむしろ逆であり、最適な動作に合わせて身体が進化した結果であるともいえる。
動作が定型となることによって、人は歩くことに意識する必要がない。つまり脳は一挙手一投足に指令を出すことなく、いつ起こるかもしれない危険に注意を向けることができる。歩く動作に脳が集中すれば、すぐに脳はオーバーワークになり「歩きながら考える」ことはできない。ましてや「走りながら考える」ことはもっとできない。一方、行為の場合は(夢遊病者の場合はよくわからないが)脳が指令(意図)を出して身体を動かす。
障害観の変化
さて、障害において上記のような原因と結果の因果モデルを転換したのは、2001年に発表されたWHOのICF(国際生活機能分類)であった。そこでは、障害があっても健康に生活するというように、障害に対する考え方が大きく変更された。
従来のICIDH(国際障害分類、1980年)における障害モデルは、「疾病の帰結」として身体の機能不全・能力低下(たとえば麻痺した手足の機能)が様々な不自由をもたらし、そのことによって社会的な不利が起こるとするものであった。障害が身体的な機能不全に起因し、その帰結は単に生活基本動作の不自由にとどまらず、様々な社会生活上の不自由と連続的に表れる。手が不自由で身の回りのことが上手にできないことから、整容が上手くできず閉じこもりがちとなり、足が弱くなり……。そのため、まず身体の機能の回復を目指し、そこから社会的不利の克服を目指す。
一方、ICFでは、障害は機能障害から医学的に規定されるものではなく、活動もまた基礎的ADLを主体とした機能でもない。機能障害の有無にかかわらずすべての人にとって認知的社会活動を含めて日常生活を円滑に遂行することが必要というものであり、「機能障害」「活動制限」「参加制約」の三つの次元は因果関係にはなく、相互作用の関係にあるとした。
ここでは、足が不自由(機能障害)で活動制限があっても、支援や介助によって皆と旅行に行ける(活動と参加)。それだけではない。「する」ことは主体的な行為であり、また、「『する』ことによって『できる』ことが増える。あるいは『する』ことがなくなることが寝たきりにつながる」(三好春樹「生活障害論」「介護技術学」)。いくら「できる」ことがあっても、しなければできることもできなくなる。主体的に活動することによって、機能の回復を目指すことができる。生活行為がリハビリテーションであると言われる由縁である。これが「生活リハビリ」の由来となる。
こうした障害観の変化は、これまでの障害への支援のあり方を動作の支援から行為の支援へと変化させる契機となった。障害の程度にかかわらず、身体的な自立に加えて社会的な自立を目指す「自立支援」という考え方もこの延長にある。
医療が動作しか対象としない、できないことが、逆に医療と異なるケアというものの固有の領域を作り出している。