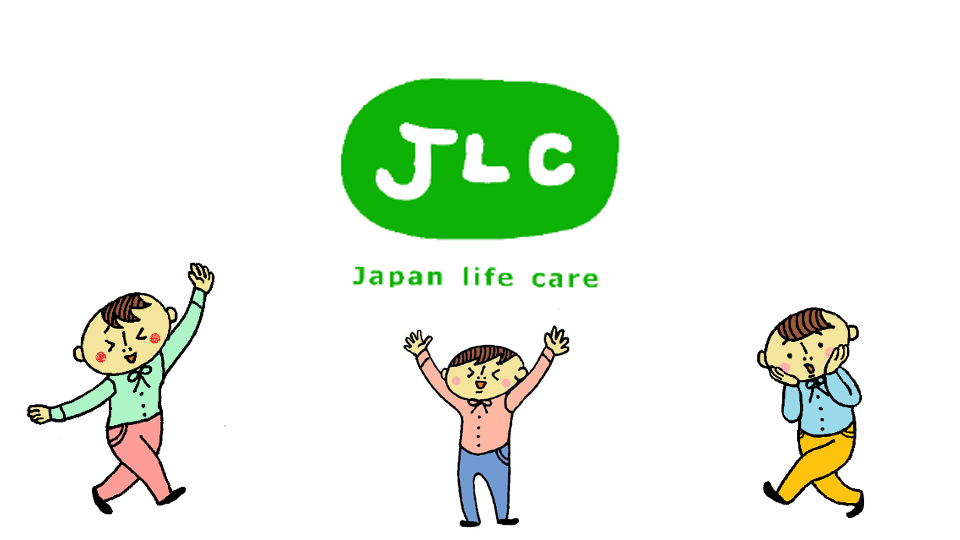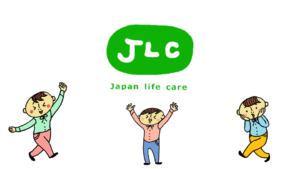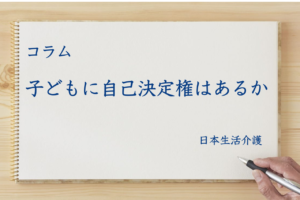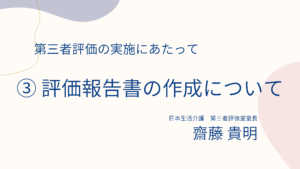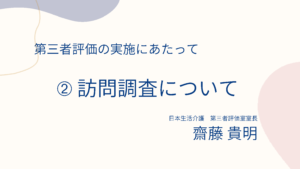2021.11
日本生活介護
倫理と道徳の違い
ケアにおいて倫理は特別な位置を持っている。ケアに携わる者は何よりも倫理的でなければならないというようにである。そして道徳もまた倫理と同じような意味で使われることが多い。両者はしばしば混同して使われるが、しかし、倫理と道徳は異なるものである。大きく言えば、道徳は個人の内面を律する個人的なものであり、宗教、思想・信条などもこれに当たる。一方の倫理は集団(共同体)や社会の理(ことわり・ルール)であり、これに従うという強制が伴う。
カント(ドイツ、18世紀)は、それまで神の命令であった倫理の原理(汝かくすべし)を人間の理性によるものへと移行した(定言命法)。しかし、その構造は神の命令と同様に、上から目線で天下り的なものとなっている。端的に批判を許さない。天下り倫理ということで言えば、わが国の「教育勅語」もまたその典型をなす。
今日、倫理と言えば欧米の功利主義(ミル、ベンサム)を指すことになる。それは、人々の幸福を最大の目的(最大多数の最大幸福)とするもので、個人の幸福(欲望)を追求する行為や手段は倫理的に正しいとされ、自由主義と民主主義の根拠ともなっている。そして、そこから法を始めとした様々な規範が導かれる。そこで対象とされるのは行為や手段であって内面の思考ではないから、内面の自由は保障されている。
付け加えれば、人びとの幸福を増進(富の拡大)する手段として科学技術の進歩も正しいとされる。確かに科学技術は人々の幸福(富)を増進させてきたし、これからも増進させるだろうと期待されている。近代の科学技術が深刻な環境問題を引き起こしたとしても、それが科学の否定(反近代)には至らない。科学が引き起こした問題であっても、それでもなお科学技術の進歩が解決するだろうと期待する。
過剰な倫理主義
それでは福祉における倫理はどうだろうか。それは功利主義の倫理なのだろうか。
通常は、理念や行動規範、倫理要綱などが事業所の倫理的な姿勢を示すものとされ、第三者評価では文書に記載された文言(テキスト)を確認することになる。その内容もまた「社会人として……」という常識的なものから、利用者のための自己犠牲をうたったものまで幅広い。しかし、総じてその特徴は倫理の著しい過剰である。
例えば、こういう例がある。今から30年ほど前の話だが、現場のワーカーたちが作った川柳が問題になったことがあるという(阿部真大「働き過ぎる若者たち」NHK出版生活人新書 2007年)。それは、問題となった川柳は、「親身面 本気じゃあたしゃ 身がもたねぇ」「ゆくたびに おなじはなしに うなずいて」といったようなもので、「感情労働たるケア労働の負担を軽減するための、ワーカーたちの重要な工夫のひとつ」(阿部)なのだが、それが、「障害者に対する差別を助長するものとしてマスコミで一斉に取り上げられ、問題となった」(福祉川柳事件)のだという。
よく「福祉は人だ」と言われるが、その場合の「人」とは倫理的個人のことである。そこに「共に生きる」あるいは「支える人と支えられる人との間に区別はあってはならない」とする思想が重ねられる。倫理は絶対善であり、批判がためらわれる。
そしてケア業界はそうした倫理的個人が集まって住んでいる世界であり、その世界を外部の人たちやメディアが賞賛するという構図が一般化されている。社会はケアに携わる人に対して、おしなべて「福祉の心」をもった倫理的個人であることを要求する
特に経営者が倫理を強調する時、それは利用者への過度の共感や奉仕を正当化する論理となり、ケア労働者の徹底的な収奪にもつながる(やりがい搾取)。そこでは、ケア労働者に対する指示は、上司ではなく倫理が命ずるというように使われ、否定を許さないものとなると同時に責任もまた曖昧なものとなる。例えば、ビックモーターの「環境整備点検」という業務命令もこれに当たるだろう。ここでもまた、業務の専門性を理解することなく環境整備という誰しも否定できない命令を統制の手段として使うことができる。
かくしてかえって倫理が口先だけのものになり、今度はコンプライアンス(法令順守)で統制しようとする。コンプライアンスとは本来企業の経営活動を対象としており、遵守義務と責任の対象は企業経営者であって個々の職員ではないが、これが倫理と混同され便利に使われている。
だが、普通に考えれば、ケア労働者は同時に賃金労働者であり、全員が常に倫理的個人であることは不可能だ。何よりもそれでは福祉事業は産業として成立しない。言うまでもなく、過剰な倫理主義は市場原理の否定であるが、市場で勝ち抜くために市場原理の否定を売りにする。ここにも新自由主義の節度のなさが見て取れる。
規範の形成と共有
だがしかし、カント流の天下り倫理を取らないとすれば、ケアの倫理に何が残るだろうか。
私たちの日常生活を律するのは天下り的な倫理ではなく規範である。
実はカント主義であれ、功利主義であれその背後には人々(社会)に共有された規範がある。規範とは、今流行の言葉で言えば「コモン」(斎藤浩平「人新世の資本論」集英社新書2020.9)といってもよい。そして、福祉の現場にあって、倫理は実際のところ共同の規範として実践されているだろう。
その規範は、社会人としてのマナーをはじめとして多様であり、数え上げればきりがない。殺してはいけない、盗んではいけない、嘘をついてはいけない、借りたものは返すなどの規範は古くから共同体が作り上げてきたものである。さらに言えば、弱いものを守るという規範は、ホモサピエンスの生存戦略ともいわれるように、すでに本能と区別がつかない自然なものとして存在している。
私たちの日常行為においておいても、歩く、話すなどの行為はとりたてて意識せずに行なわれるが、動作や行為は単に骨格や筋肉(そして重力)などによって制約されるたけでなく、社会的にも制約される。目を合わせて話す、背筋を伸ばして歩く、箸を正しく持って食べる、あるいはマナーなどのように、そこには常に共同の規範が入り込んでいる。
このように、動作や行為は歴史的に形成された公共的(社会的)なものであり、規範は人の「第二の本性」として社会に強く根付いている。そして子供はこの「第二の本性」を成長の過程で「身に着ける」。
人は規範を内面化しながら、集団(共同体)を形成する。そして、国家や地域には国民性や風土、しきたり、学校や企業には校風や社風、そして家族には家風と呼ばれるような様々な規範がある。規範の共有がなければ共同体は成立しないし、共同体の規範を共有できなければ生きづらさにもつながる。
今日では、一般的に共同や共同体はコミュニティと言い換えられ、よきものとして扱われるが、共同体は仲間を温かく迎え入れると同時に他者に対しては排他的なものであり、かつては共同体の規範を共有しない人々は異邦人と呼ばれ排除の対象だった。この排他性もまた共同体の特性である。さらに、規範は属する共同体での役割に応じても使い分けられる。一人の個人も職場、学校、家庭で社員や生徒、親などとしてそれぞれの規範に応じた社会的役割を演じる。普段はいい加減な父親であっても、子どもが学校なので逸脱した行為をすれば、社会を代表してわが子に世の中の規範を説教するだろう。
こうした規範が生まれることについて、アダム・スミスは「道徳感情論」(1759年)において、規範は神の命によるものではなく人々の感情交換が生み出すのだと説明する。感情の表出(感情そのものではない)を通じて人々に一定の共通の価値判断が共有され、さらに他の集団の成員と同様の感情交換が幾重にも繰り返されることを通じて、社会的な共通の価値判断(社会的規範や法律)が形成されるという。
重要なことは、倫理が天下り的に与えられるのではなく、人々のコミュニケーションを通じて、規範を作り出すということである。それは欲望に支配された個々人が、みえざる神の手に導かれて市場のルールを作り出していくという「国富論」のロジックと重なっている。
特にケアにおいて、支援者がスキルを行使して利用者の技能に介入する時、その行為は利用者に対して、快・不快、同意、適切・不適切かどうかといった規範をまといながら実行される。こうしたことは、なかなか言葉でうまく表現すること難しく、例えば、他人の逸脱した行為を見た時に、目に余る、度を超す、ちょっとやりすぎなどというように感じられるようなものであり、これが、「規範」が共有されていることの内実となる。だから、職員間で倫理(規範)を共有するということは、事業所の示す倫理のテキストを読むことでも、唱和することでもなく、技能の共有のことである。
規範をつくり変える
規範は集団(共同体)が形成したものだから、したがって、規範は共同体の数だけ存在すると見なければならない。しかし、ここで共有された規範はその集団に固有のものであり、集団は私の集団である。しかし、例えば「〇〇の常識は、社会の非常識」という言葉があるように、私の集団の規範が一般的なものかどうかは、その集団の内部にあってはわからない。私の集団の規範を知るためには、私の集団を否定する他の集団が必要である。私は、私の集団から外部に出て他の集団の規範を知り、ここで初めて自分たちが当たり前のこととして考えていた規範が、実は自分たちに固有の振る舞い方であったことを知る。あたかも海外旅行をして、かえって日本のことを知るように、である。
他集団と交流することは、だから、他の集団を知ることなのではなく、実は、他集団を通して私の集団を知ることである。他集団との相違の感覚は、当然にもデータの比較ではないから、言葉にできない何かしらの違和感としてしか言いようがないようなものとなるだろう。その違和感の根拠を探しながら私の集団を知るのである。
このように、規範は絶対的なものではなく、共同体によって異なり、また、絶えず変化する。このことは、逆に規範を自分たちで作り上げることが可能なことを示している。
一般的に規範が大きく変わるのは、例えば外圧のように、共同体が危機に直面した場合である。「このままでいいのか」「これではだめだ」という意識が共同の主観として形成され、共同体の規範(価値観)はダイナミックに変化する。
通常の場合、自らの規範を意識的に点検し修正することはなかなか難しいが、こうした試みに積極的に取組んでいる事業所もある。ある事業所では、「〇〇ゼミ」という試みを毎月行っていて、ケアにおけるグレーゾーン、例えば呼称(〇〇さん、様、ちゃん)の妥当性を職員たちが議論している。仮に結論がでないとしても意味あることだろう。それは議論への同意・反発の過程で自らの規範の自覚(みえる化)につながっているからである。
第三者評価の意味は、一つの集団に対して、外部(社会)の目を持ち込むことと言われるが、その時、評価者集団は組織の掲げる倫理にではなく社会の規範(常識)を尺度として支援のあり方の是非を判断することになる。そこに違和感があれば、評価者同士の合議の場面で他者の規範と比較を通じてその原因を考え、誤解によるものかあるいは正しかったのかについて自分なりに納得すること、この繰り返しが第三者評価者のスキル(専門性)となる。
ここから全文がダウンロードできます。